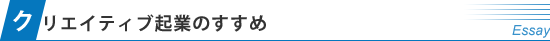怒りが世を動かす「ダラス・バイヤーズクラブ」
HIV陽性で、余命30日を宣告された男の物語
「ダラス・バイヤーズクラブ」を観た。低予算映画ながら、今年のアカデミー賞で、主演男優賞(マシュー・マコナヘイ)と助演男優賞(ジャレッド・レト)を受賞した作品だ。
公開前、チラシを見かけた時から気になっていたが、予想にたがわず面白い。サンフランシスコ市内の映画館に行ったが時間が合わず、自宅ケーブルテレビで1回(6ドル位)、日本往復の飛行機内で字幕付きで2回、計3回も観てしまった。
物語は、1985年のテキサスで起きた実話がもとになっている。HIV陽性で余命30日を宣告された男が、米国内で未承認だった治療薬をメキシコなどから手に入れ、有料の会員制システムをつくることで、患者たちにさばいた、という話。男は、その後7年間生きるが、ちっぽけな田舎の弱者が、腐敗した権力に立ち向かうという構造は、ハリウッドらしいヒーローモノでもある。
今僕が書いている「起業家の映画」のヒントになることが、いくつもあった。
強烈な主人公のキャラクター
主人公ロンのキャラクターが強烈だ。40代独身の電気工で、トレーラーハウスに住み、工事現場で働く。趣味は、ロデオライドとギャンブル。
一人身をいいことに、追っかけの女のコたちを家に連れ込み、友人のロデオライダーとパーティー三昧。きついウイスキーやマリファナを楽しむような、自堕落で、自由気ままな暮らしを謳歌している。性格は短気で、気に入らないと誰彼かまわず、すぐに噛みつく。人に好かれるタイプではなく、物語の主人公としても観客は共感しづらい。物語の前半までは。
そのロンが、HIVに感染し、余命30日を告げられる。最初「オレはゲイじゃないから、そんな病気ありえない」と医者に噛みつくが、体調は悪化する一方。治療薬を求めるロンは、やがて、驚きの事実を知ることになる。米国では、他国では承認されている有効な治療薬が、なぜか承認されていないのだ。ロンは、治療薬を求めメキシコの闇医者を訪ねるが、やがて、その薬を米国内に持ち込み、エイズ患者にさばき稼ぐことを思いつく。 この過程で、ロンは、自分の主治医に悪態をつき、FDA(厚生省のような役所)の集会に怒鳴り込む。
のめり込みや怒りが、新しいものを生み出す
面白いのは、ロンの怒りやのめり込みが、意図せずして、FDAと製薬会社の癒着を糾弾し、エイズ患者への治療薬の配布に一役買うこと。
ただし、ロンは決して正義の味方ではない。ゲイを頭から毛嫌いする態度は偏見に満ちているし、会費を払わない患者に薬を無料で与えることはしない。なにより、政府との戦いは、患者たちを助けるためではなく、自分が生き延びるために始めたのだ。
僕が一番おもしろかったのは、この、ロンの利己的な怒りが世の中を動かす、という部分だ。
起業の世界でよく耳にするのだが、人が起業するのは、「お金持ちになりたい」「この事業を成功させたい」という動機が最初からあるのではない、ということだ。最初から起業を狙うのではなく、「これは面白い」という事にのめり込んで行ったり、「なんでダメなんだ?」と、今いる社会に対する怒りから物事を進めていくと、その結果、起業に至る、という事が多いそうだ。自分の経験に照らしてもうなずける話である。自分がやりたい事を追求していくと、古臭い常識や大企業が支配する旧体制などが阻害してくるので、それを打ち破らないと先へ進めなくなってしまうのだ。
やってきたことに意味があったのか?
映画後半に、感傷的な名シーンが一つある。ロンを心配し、女医が自宅に訪ねてくる。体調最悪のロンは、女医に抱かれながら気弱にささやく。「こんなに生き長らえることができるんだったなら、旅行とか、もっと人生を楽しむことをやるべきだったかな?国との争いなどせずに」。数少ない味方である女医は、ロンの体を優しくなでながら、「あなたは、意味のある人生を生きているわ」と励ますのだ。
実在の人物、ロン・ウッドルーフは、行きがかり上、政府と対立するようになったが、生前(今から20年前!)、取材に来た脚本家に、「自分の話が映画になるなら、是非観てみたい。やってきたことに意味があったんだと思えるといいな」と語ったそうだ。
以上